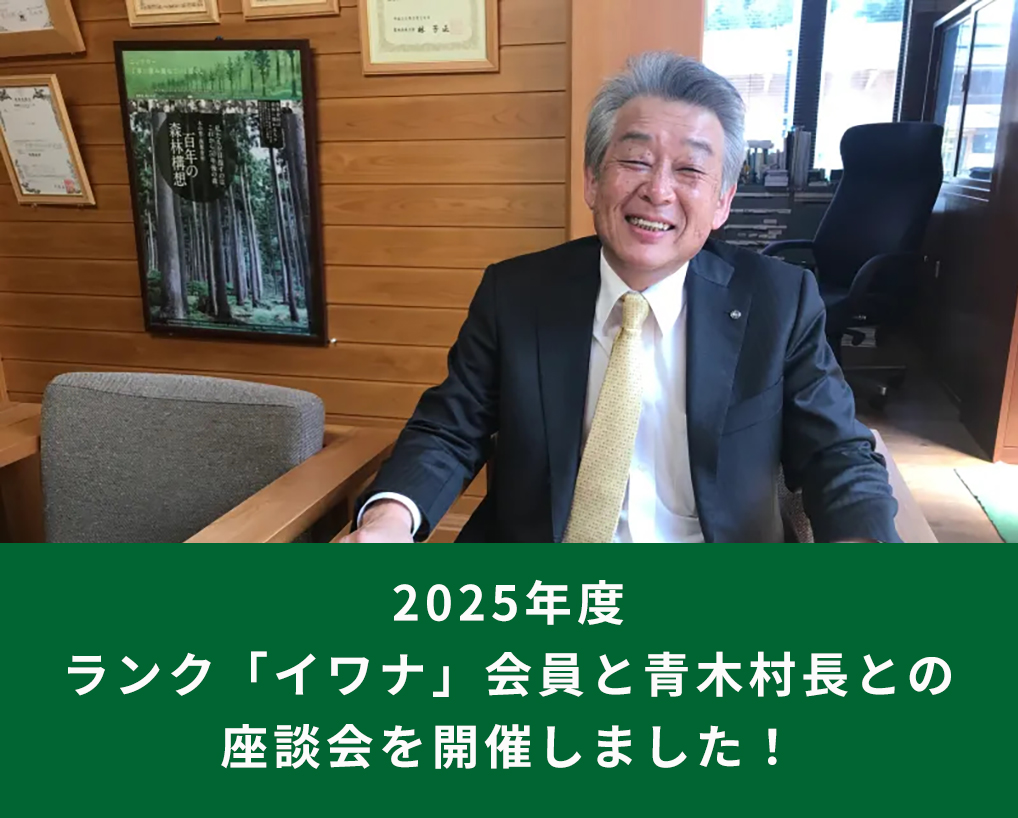
この対談の感想をお伺いするアンケートを実施しています。本文の最後からご案内していますので是非ご回答ください!
アプリ村民票の高ランクの会員の方向けの特典として、2025年8月に第二回目となるアプリ村民と青木村長との座談会を開催しました。
今回座談会に参加している皆さんはいわゆる「関係人口」という形で村外に居住しながら、西粟倉村に関わっています。今回は西粟倉村の現状と展望を青木村長に伺いながら、関係人口がどういう形で関わっていけるのか、一緒に発展を築いていくことができるのかを考える機会となりました。

自己紹介
春名さん:春名淳嗣と申します。今は大阪在住ですが、もともと父が隣町の大原町の江ノ原出身で、親戚も西粟倉でしたら筏津の方におります。
小さい頃は、夏休みとかずっと遊びに行って、過ごしておりました。その後、就職して社会人になってからは、だんだん疎遠にはなっていたのですが、最近すごく西粟倉さんが頑張っておられるとのことで、いろいろと私でも応援できることがあればと、参加させていただくようになりました。
平田さん:平田将士と申します。私も父が西粟倉の引谷出身で、私自身は生まれても育ってもいないのですが、現在は母が一人で西粟倉村に住んでいるのと、山林を引き継いだので、年に2回とか3回とかぐらいのペースで西粟倉に帰っています。
青木村長:西粟倉村村長の青木秀樹です。
私は今4期目になっていまして、年齢も70歳になりました。最近ちょっと歳を寄せていくと、いろんなところに不具合が出るなというふうに感じつつありながら、皆さんまだ若いので負けないように頑張らないといけないなというふうに思っています。皆さんのいろんなお知恵や体験とか、いろんなことをお話の中で触れながら、それを活かしていきたいなというふうに思っています。
西粟倉村の現在
青木村長:西粟倉村は、昭和25年ぐらいには人口が3000人を超えていたという記録がありますけれども、現在は約1300人の人口になっています。平成の大合併が2004年、当時はおそらく1600人ぐらいいたと思うんですけれども、それからすでに300人ぐらい減っています。
ですが、こんな山奥の地域でも、人口の2割がIターン、特に都市部からの移住者が多いんです。そういう地域は本当に珍しいと言われていますし、そういう動きが出始めてから15、6年経ちますが、あと10年経てば人口の半分は移住者になるくらいの状況だと思います。
西粟倉村は若い企業家、ベンチャー企業を呼び込む取り組みを長くおこなっています。受け入れ体制やサポート体制もありますし、移住者がチャレンジする仕組みがありますので、そういうところが移住者を呼び込む結果につながっていると思います。
西粟倉村は、いろんな意味で多様性のある自治体になっています。山のことを一生懸命やっている方もいるし、IT関係や、例えばデザインに関する仕事をしている方は7人もいます。この小さな村にデザイナーとして飯を食っている人が7人もいるというのは驚くべきことなんです。関係人口も含めて、いろんな関わりで人が増えてくるということ。この多様性をさらに広げていくということが、この村の持続性をもっと上げていくことに繋がると思っています。
どんどん変わっていくなと。変わっていかなければ、西粟倉村のような小さい村は続けられないのかなと。
平田さん:そうですね。村長がおっしゃるように人口が減るということは、いろんな制約ができるので、それをなんとか増やしていきたいというのは、そうなんだろうなと思うんです。関係人口、実は今日丸山さんや高嶋さん(アプリ村民票運営担当)が、実は村民の方ではないということを聞いて、ちょっと驚いたんです。
また、以前新聞の記事で青木村長が「アプリ村民からも徴税をする」ということを一つのアイデアとしてインタビューで発言されていましたが、関係人口側が得られるメリットが何になるのかっていうところも含めて、どんなようなビジョンがあるのかすごく興味があるところでした。
青木村長:今、総務省が主導している「ふるさと住民登録制度」という構想があります。これはまだ構想としてきちんとまとまってはいないのですが、自分の心のふるさと、それを帰属意識として持ってもらう、そういう関係を地方自治体と関係人口の間で作ろうという制度だと理解しています。西粟倉村のアプリ村民票は、この動きを先行しておこなってきた事例とも言えます。西粟倉村と個人がアプリを通じて関係性を持つことで、タイムリーに村の情報を得ることができたり、村で行われていることや、イベント、あるいは村で生産したり、販売しているものをふるさと納税などの経路も含め、村外からアクセスできる仕組みとして既に確立しているという特長があります。
平田さん:総務省の狙いは最終的に何らかの経済活動なり人的交流なりにつなげる前提で、その前にまずはそれぞれの自治体を知ってもらって、親しみを持ってもらい、そこから何らかのアイデアが創出されること期待するという感じでしょうか。
青木村長:そうですね。現代社会、特に都市部では非常に関係性が希薄になっていると感じます。都市部の人がどこかに帰属しているという感覚を、日本全国の様々な都市、地域に対して持つことができれば、ある種の安心感と責任感を得ることができる。ふるさと住民登録制度はそれをきっかけに都市と地方とのパイプを作って、経済的な効果やより活発なネットワークを作っていくことを狙っているのだと思います。
春名さん:私がアプリ村民票を登録させてもらったのは、やはりどうしても村に帰ったりしないと、村の状況がわからない。年に一回、お盆の帰省の際に親戚同士で集まって話しをしないと情報が入ってこなかった。それがアプリ村民票に登録することで、また村とのつながりが保てて、いろいろな情報をもらったりとか。昨年もオオサンショウウオを見に行くツアーというのをアプリ村民票の告知で知りまして、参加することができました。子どもたちが川に飛び込んだり、魚を探したり。ああいう企画は非常に面白いですよね。
青木村長:今の子どもたちはそういうことをあまり経験していないんです。昔はそれしか遊びがなかったし、夏は川で遊ぶくらいしかすることがなかった。それが思い出として非常に記憶に残っているのですが、西粟倉村では今の子どもたちがそんな体験もできるような工夫もしています。
春名さん:そうですね。やっぱり小さい頃に経験したことって大きくなっても忘れないんで、私としてものすごく懐かしいなと思って遊ばせてもらいましたし、いまの子どもたちは、水族館で見るのと、天然のオオサンショウウオを見るのとではやはり違うと思います。アプリをきっかけにああいう催しに参加できるというのはものすごく良かった。
村の林業・農業
青木村長:西粟倉村というところは昔からですね、もう本当に産業のない村です。明治以降、林業が根付きました。そのころは山や木材の価値が非常に高かったんですね。木材の価格は昭和55年頃をピークに現在では20分の1になっています。生やさしい価値の低下ではない。
現在の林業は木を切って持ち出す経費が非常に高くなっているので、利益がなかなか発生しないという問題があります。それを解決するために、西粟倉村が推進する百年の森事業では、山林をある程度大きくまとめて、合理的に間伐することによって管理コストを下げて、山主さんが個人個人でやるよりもはるかに高いパフォーマンスで維持管理することを実現しています。間伐によって山の地面に光が射し、森林の成長が促進される良い山にして、間伐によって生まれた利益を山主さんにお返しをするというシステムですね。
平田さん:私は山主として株式会社百森さんに管理をお任せしています。九州の有名な林業をやられている方がおっしゃっていましたが、一本一本の木を管理することで、安定した同一品質の木を作り続けることで産業として成立させる必要があると。おそらく西粟倉村では株式会社百森さんがその役割を担っておられるんだろうなと。その活動がどのように実を結んでいくか非常に楽しみにしています。
青木村長:そうですね。そうだと思います。村の財源を民間山林の整備に投入するというこのシステムを、主体的にやり始めたのは西粟倉村が日本で唯一だと思います。
平田さん:まさに村長がおっしゃったように、木材の価値が20分の1という状況で、その問題を放棄するのではなく、直視して取り組んでいることについて非常に感銘を受けています。たまたま西粟倉村の山主だからということではなく、そこにあるものを活かすことを一生懸命考えれば解決策が絶対に出てくると思っているので、それは素晴らしいなと感じています。
皆さんは既にご存知かもしれませんが、東京では毎年林業関連のフォーラムが開催されています。林業で働きたい人向けに仕事の紹介をおこなっているようなフォーラムですね。私は毎年そのフォーラムに参加しているのですが、驚いたのはせいぜい100人程度の参加者規模かと思いきや、毎年数百人は参加しているようなんです。そして大半の見かける方は20代や30代。そしてもっと驚いたのは3割程度が女性の参加者なんです。
ただし東京開催のフォーラムなので、人気のブースは首都圏近隣、ないしは大都市近隣の求人のようです。その意味では西粟倉村は少し距離がありますが、林業に興味を持つ若い人が増えていて、西粟倉村のような自治体との関わりを求めている方が増えているのだろうと実感した次第です。
青木村長:私はこれから特に農業を目指す若い人たちが西粟倉村に必要だと思っています。西粟倉村がこれから生き残っていくために何が大事かを考えたときに、大袈裟かもしれませんが小さい村でも日本全体に発信できるモデルのような場所になる必要があると考えています。エネルギーの分野や、林業・木材加工の分野ではある程度実現してきました。
そしてこれからは農業、食料の分野だと思います。日本は食料自給率が低く、輸入に頼っている部分があるわけですが、その問題をこの小さい地域で、モデル的に取り組んで食料の実給率を上げていくことができればと思います。お米は比較的自給できていると思いますが、他の野菜や穀物はまだまだ取り組む余地があると思います。
村の観光
青木村長:西粟倉村の観光資源はなにかと考えると、やはり自然という話になるのですが、村で起業したローカルベンチャー企業が、それぞれいろんな取り組みをやっているので、それを見て回るだけでも結構な気づきが生まれることがある気がします。
それと、林業だけでなく、森林空間をいかに活用するかということも観光資源になると感じています。昨年は西粟倉村の森林を使って「森々燦々」という芸術祭を開催しましたが、それを経て様々なアイデアが出てきており、今後どんなことに発展していくのか非常に楽しみでです。
また、観光というと「食」は外せません。例えばこれは村内の出身者なんですけど、「小林菓子店」というケーキ屋さんを始められて、結構遠くからそこを目当てに多くのお客さんが来村しているケースがありますし、天徳寺という古いお寺にある古民家を改装した「あるの森」という宿泊もできるタイ料理レストランがありますが、周辺地域の方を含め結構遠くから来客される現状もあります。
西粟倉の「食」という部分は徐々に揃っているんですけど、先ほども言いましたように、農業を含め「食をつくる」ということに、闘志を燃やす若い人がもっと出てきて欲しいなということと、それから山の資源、山の有機物と言いますかね。地域で一番豊富な資源ですね。そういうものを活用して、例えば山の有機物を活用した無肥料・無農薬で育てる野菜。それは非常に付加価値が高くなるんじゃないかなと。それで野菜とか果物とかを作ってもらいたいなと。私自身も個人で試験的にやっているんですよ。
村への移住環境
春名さん:昔は田舎だと住むところはいくらでもあるけれど、仕事がないという状態だったと思いますが、今の西粟倉村のようなところは逆に色々なベンチャーができて人手は欲しいけれど、田舎なので人がなかなか集まらない。都会みたいにマンションがあるわけではないので、若い人が住みやすいような、移住してすぐに住める環境を整備するのがなかなか難しいのかなと思います。
青木村長:今は昔とだいぶ生活スタイルと価値観が変わってきていますね。大きな家を欲しがるというよりは、なるべくコンパクトな方が人気だと思います。ただ、その価値観がずっと続くんだろうかと言うと、それはそれでわかりません。
例えば村にあるような古い一軒家ですが、それを昔の通りに使おうと思ったら大変です。それを新しい使い方に変えていくと、すごく価値が高くなるということが実際にあったりします。その時代に合った利用の仕方を考えることが大切だと。ですから、粗末にしないで管理だけはしっかりしておくということも本当は大事なことなのかなというふうに考えますね。
平田さん:最近選挙なんかで外国人に対する違和感というか、文化の違うに対するわりとはっきりとした拒絶みたいなものが表面化していると思います。今まで暮らしてきた、背負ってきたカルチャーだとか、そういうことの違いが顕著にでているということだと思いますが、ずっと西粟倉村にいた人と、都市部から移住してきた人でも、同じ日本人でも本質的に違うものを持っているところがあるんじゃないかなと思います。そこのすり合わせというか、対話するための仕掛けみたいなことはどうされていますか。
青木村長:西粟倉村のように急激に都市部から若い人が移住してくると、悪意はなくともいくらか考え方が違ったり、今までの生活スタイルが違ったりして、すんなりと地域住民と理解し合うことができないこともあると思います。
ただ、西粟倉村では不思議なことが起こっているんです。村には消防団がありますが、移住してきた若い人たちの多くが消防団に入ってくれているんです。これはね、すごいなと思う。彼らの地域へのアプローチや属性の高め方というのは。消防団なんて若い人には面倒な活動ですから。全国にある多くの消防団は若い人が集まらず困っている状況です。移住者も一緒に地域の安全を守れているというのは非常にありがたいし、素晴らしいです。
古いやり方を守ることも大事なんですけども、どんどん人間の生活は変化するので、地域としてある程度進化、変化していくことによって持続性がついてくるなと感じますね。
村の教育
青木村長:地域を守るってことは、その地域に人を育てる力があるということが絶対に必要なんだと思います。人を育てることができなくなった地域は、役割を失います。なので、西粟倉村でも教育は重要なテーマです。
学歴のための教育ではなく、自分がどうやって社会課題を解決していくのか、そういう力があるかということが問われる時代ですから、若いうちからそういうことに敏感で、気づきを持った子供を育てていくということ。自然の中でいろんなことを体験しながら、できるだけ学んだことは時間を置かずアウトプットして、自分の気づきや成長に換えていくことが、西粟倉村の教育でできたらすごいなと思っています。
最後に
平田さん:青木村長もまだまだ若々しくて、エネルギーを一杯いただいたように思います。お話を伺いながら、いろいろと思ったこともありましたので、皆さんとまた考える機会があればなというふうに思っています。
春名さん:現在は大阪に住んでいるので、なかなか村に帰ってきて何かお手伝いをするのは難しいですが、離れたところからでもできるような、大阪万博でもおこなったような西粟倉村を知らない方に知ってもらう支援活動などをお手伝いする機会があればぜひ参加させていただきたいと思います。
参加いただいたアプリ村民のご両名と青木村長、ありがとうございました!
この対談の感想をお伺いするアンケートを実施しています。是非ご回答ください!
【スマートフォンから回答される方】
西粟倉アプリ村民票を起動し、画面下のメニュー「アンケート」からご回答ください。
【PCから回答される方】
まず、ログインを求められた場合のログイン情報(登録メールアドレスとパスワード)の確認をお願いします。
メールアドレスは、当メルマガが配信されるアドレスです。
パスワードをお忘れの方、不安な方は下記ページで再設定をお願いします。
https://www.24h-life.jp/forgot-password
ログイン情報が確認できましたら、以下のページから回答をお願いします。